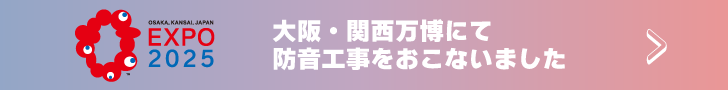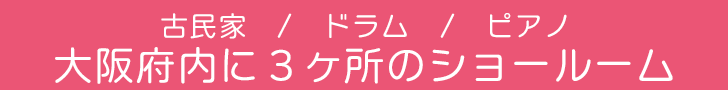防音室に必要な性能を目的別にご紹介!防音リフォームのデメリットも

サンテレビ「アサスマ! 」で防音工事の匠が紹介されました!
人々の生活空間が近くなっている昨今では、楽器の演奏など、大きな音を生じさせるような行為は、近隣住民に配慮するためにも防音対策が求められるようになっています。
実際に、自宅でピアノなどの楽器を演奏する、ホームシアターを設置する、カラオケを楽しむなど、大きな音が生じると想定できるような場合、専門業者に依頼して防音室を作るという対策が一般的です。ただ、一口に「防音室を作る」と言っても、中でどのような音を生じさせるのかによって必要になる性能は大きく変わるのです。当然、防音室を作るためにかかる費用については、高性能な物ほど高くなっていくため、無駄なコストをかけないようにするためには、自分が出すと想定される音に対して、ジャストスペックな防音室がどのような性能なのか判断しなければいけません。
そこでこの記事では、防音室に必要と考えられる性能について、目的別にご紹介していきたいと思います。
目的別!防音室に必要な性能について
防音室は、中で生じさせる音の大きさや種類によって必要になる性能が変わります。当然、防音室に求められる性能が変われば、リフォーム工事の費用も変わるため、不必要なほど高性能な防音室にしないためには、目的別に求められる防音性能をおさえておく必要があります。
ここでは、防音室の中で演奏する楽器などによって変わる防音室の性能について解説します。
ピアノの演奏が目的の防音室
防音室のご相談として最も多いと考えられるのが、ピアノの演奏を目的としたものです。ピアノは小さなお子様の情操教育にも利用されることが多いのですが、演奏時には大きな音と振動が生じるため、近隣の方に配慮するためには、防音室が必須と言える設備になります。実際に、日本国内で防音工事が注目された理由は、過去に起きたピアノの演奏音による重大トラブルが起因とされています。
ピアノの演奏を目的とした防音室は、空気音を遮断するための遮音や吸音の性能が求められるのは当然として、ペダルを踏んだ時の振動やピアノ本体の振動が階下に伝わらないようにするための振動対策が求められます。そのため、ピアノの上達を目的とした本格的な防音室の場合、部屋全体を二重構造にするなど、かなり高性能な防音室が作られます。
遮音等級などで表すと、「D-55以上」など、かなり高い性能が必要になるので、工事にかかる費用はそれなりに高額になると考えておきましょう。
木管楽器の演奏が目的の防音室
木管楽器は、「木を主原料とした楽器」ではありません。木管楽器と金管楽器の違いは、音の出し方で決まるので、その点は押さえておきましょう。代表的な木管楽器と言えば、フルートやクラリネットがありますが、この他にもサックスなど、大きな音が生じる楽器があり、それぞれ特性に合わせて防音環境を構築しなければいけません。
例えば、以下のような感じです。
- フルートやクラリネット
フルートやクラリネットは、木管楽器の中でも高めの音を発生させる楽器です。そのため、比較的防音効果を発揮しやすいタイプと言えます。また、ピアノと異なり、楽器そのものが床に接しているわけではないため、振動の対策などもそこまで難しくありません。一般的には、90dB程度の音量となる楽器なのですが、自宅で演奏を検討している場合、「D-35以上」の遮音等級を目安として防音室を作れば良いでしょう。 - サックス
サックスにも、ソプラノサックス、アルトサックス、テナーサックス、バリトンサックスなど、いくつかの種類があるのですが、特に低音を発するテナーサックスやバリトンサックスは防音しにくいタイプと言えます。さらに、サックスは、初心者の場合、練習の際にも音が大きくなりやすいと言われているため、フルート用の防音室よりも高い性能が求められます。サックスは、100dB程度の音量を想定して、「D-40~50」の防音性能が求められると考えておきましょう。
金管楽器の演奏が目的の防音室
次は金管楽器です。トランペットやトロンボーンなどが金管楽器に分類されるのですが、マウスピースに唇を当て、唇の振動で音を出すという点が特徴です。金管楽器は、そもそも音が大きくなりやすいという特性を持っているのですが、その他にもトロンボーンなど、演奏時の動作に必要なスペースを確保しなけれレばならないタイプがあるため、広さなどにも注目する必要があります。
- トランペット
トランペットは、サックスと同様に、音が大きくなりやすい楽器です。それなりの技量の方であれば、100~110dBもの大きな音が発生するとされています。ただ、トランペットは、中高音域の音に該当するため、防音のことだけを考えると、比較的容易な楽器となります。したがって、防音性能としては、サックスよりも落としても大丈夫で「D-35以上」を目安と考えましょう。なお、トランペットなどは、楽器の先端についた広がった部分(ベルと呼ばれます)から音が出るのですが、ベルの向きを工夫することで、防音室の性能をもう少し抑えることも可能です。 - トロンボーン
トロンボーンは、音量そのものはトランペットと同様に110dB程度です。ただ、ベルが大きく、低音も出るという特徴から、防音の難易度は高くなり、音への配慮が必要です。ベルの向きを、音に配慮しなければならない方向とは逆にするという工夫を実施すれば、トランペットと同様に「D-35以上」の防音性能を目安にすれば良いでしょう。四方を家に囲まれているといった住宅密集地や集合住宅の場合は、もう少し高い性能を目指しましょう。
弦楽器の演奏が目的の防音室
弦楽器もさまざまなタイプがあります。ヴァイオリンやアコースティックギターなどの場合、そこまで高い性能は求められませんが、エレキギターをアンプに接続して演奏する場合は、非常に大きな音になるので注意が必要です。
- ヴァイオリン
ヴァイオリンは、音量そのものは100~110dBほどと、それなりに大きな音が出ます。しかし、発せられる音は高音域に該当するため、防音環境は構築しやすいです。そのため、ヴァイオリン用の防音室に求められる性能としては「D-35以上」を目安にすると良いです。注意点としては、演奏時の動きを想定する必要があり、それなりのスペースと天井高を確保しなければいけません。 - アコースティックギター
アコースティックギターは、ヴァイオリンよりも音が小さく、80dB程度の音量です。ただ、ヴァイオリンと比較すると、低音域の音となるので、防音性能としては「D-35以上」あたりを目安としておくのが無難です。 - エレキギター
エレキギターは、アンプに接続して演奏する場合、110dB以上の音量となります。そのため、、楽器音の音圧と周波数特性から、最低でも「D-50以上」を目安としましょう。ちなみに、集合住宅に作る防音室については、「D-60以上」が目安です。
ドラムなどの打楽器の演奏が目的の防音室
防音室工事の中でも、特に高い性能が求められるのが、ドラムなど打楽器用の防音室です。ピアノと比較しても、さらに高い遮音性能が求められると考えておきましょう。
特に、閑静な住宅街の場合、防音室を作っても音が響くことがあると言われていますし、ドラムの重低音は床や壁など低い部分を伝わりやすいです。そのため、しっかりとした性能の防音室にするためには、コンクリート工事などを行って対策を行う必要が出てくる場合もあります。集合住宅になると、ドラム用の防音室は断られるケースも多いので、注意しましょう。
ホームシアターやカラオケが目的の防音室
最後は、ホームシアターやカラオケを目的とする防音室についてです。これについては、導入するスピーカーシステムの性能などによっても、必要な防音性能が変わるので、基本的には防音工事を依頼する業者に、要望をしっかりと伝えることで、必要な性能を提案してもらうと良いです。
ただ、ホームシアターなどについては、音漏れだけでなく、外部からの音の侵入も防ぎたいはずです。映画などに没頭するためには、外部騒音の侵入を防がなければならないため、「D-60〜70」前後の高い防音性能を目指すのがおすすめです。
防音室作りで注意したいデメリット面について
ここまでの解説で、一口に防音室と言っても、利用目的によって必要になる防音性能が変わるということが分かっていただけたと思います。それでは、実際に防音室工事を専門業者に依頼しようと考えた時、注意しておきたいデメリット面とは、どのようなことがあるのかについてもご紹介します。
費用について
最もわかりやすいデメリットは、防音室を作るためには高額な費用がかかってしまうという点です。特に、遮音性能が高い防音室の場合、どうしても施工費用が高くなってしまい、6畳程度の防音室でも200万円前後の費用がかかってしまうことになります。防音工事にかかる費用については、工事を依頼する業者や求める性能によって上下するのですが、一般的な相場は以下のような感じです。
- ・ピアノ用防音室:150〜400万円(6畳程度)
- ・管楽器用防音室:150万~300万円(6畳程度)
- ・ドラム練習用の部屋:350〜550万円(6畳程度)
- ・オーディオルーム・ホームシアター:150〜300万円(6畳程度)
- ・組み立て式 防音ユニット/ボックス:45〜300万円
上記はあくまでも参考程度で考えてください。ユニット型の防音室であれば費用は押さえられるものの、音響環境の調整などが難しいため、ストレスなく長時間の練習をしたいという場合には不向きです。
メンテナンスについて
二つ目は、メンテナンスについてです。防音室は、一度完成したら、その性能を一生保ってくれるといった物ではありません。想定した性能を維持していくためには、定期的なメンテナンスによって防音室の性能を保たなければならないのです。
防音室に採用される遮音材や防振材、吸音材などの建材にも経年劣化というものがあります。例えば、防振マットや吸音を目的に施工されるグラスウールは、10〜20年ほどで性能が低下することがあるとされているため、音漏れなど防音室の性能低下を感じた時には、遮音測定や部材の交換を検討しなければいけません。
この他、防音ドアや窓に関しても、パッキンの劣化やヒンジの緩みなどが音漏れの原因となるため、定期的な点検と、必要に応じて部材の交換といったメンテナンスが必要になります。つまり、防音室は、メンテナンスのためにそれなりのコストが将来的にもかかる可能性があるという点がデメリットです。
まとめ
今回は、楽器用の防音室などについて、用途別にどの程度の性能が必要になるのかについて解説しました。
記事内でご紹介したように、演奏を予定している楽器の種類によって、防音室に求められる性能は大きく変わります。そのため防音リフォーム工事に不必要な費用をかけないようにするためには、何のために防音室を作りたいのかを明確にしたうえで、それを正確に施工業者に伝えることが大切になるのです。防音工事の失敗事例でよくあるのは、お客様と施工業者の間に認識のズレがあるというパターンで、本来必要になる性能が確保されていなかったという状態になってしまうことが多いです。
防音工事は、その他の住宅リフォームと比較しても、決して安価な工事ではないため、失敗しない、また無駄なコストをかけないためにも、防音室の用途を事前に明確にすることが大切と考えてください。