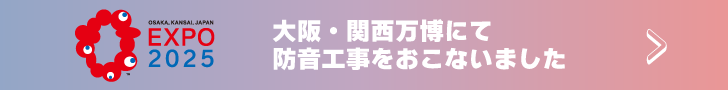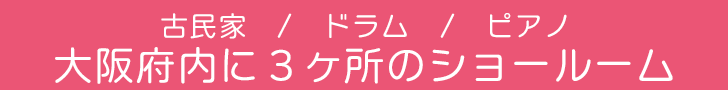防音壁の基礎知識。防音室に使われる防音壁材についてご紹介

サンテレビ「アサスマ! 」で防音工事の匠が紹介されました!
防音室と聞くと、室内で楽器の演奏を行うなど、大きな音を生じさせたとしても、室外にその音が漏れていかない部屋を想像する方がほとんどだと思います。実際に、防音室は、主に隣人との騒音トラブルを防止するという、近隣配慮を目的に作られるケースが多いです。
そのため、防音室の壁については、とにかく室外に音漏れしていかないようにするため、遮音性能を高めれば良いと考えてしまう人がいます。昨今では、ホームセンターなどで本格的な防音材が購入できることもあり、DIYで防音室を作ろうとして小手先の防音対策に走る方が多いのです。しかし、楽器の演奏などを目的とした防音室の場合、適切な壁材を採用した防音壁を構築しないと、防音室の利用時に困ってしまうケースがあるのです。防音室は、単に音漏れを防げれば良いというほど単純なものではなく、利用者が快適に過ごせる環境を作り上げる必要があるわけです。
もちろん、専門業者に依頼して高性能な防音室を作る場合、それなりのコストがかかってしまいますが、周囲に気兼ねなく、さらに快適に利用できる防音室にしたい場合、防音壁の構造や性能にきちんと注目しなければいけません。そこでこの記事では、防音室の壁に求められる性能や、それを実現するための防音壁材の種類について解説します。
防音室の防音壁に求められること
防音室の防音壁は、主に室内で発生した音や振動を室外に漏れていくのを防ぐということが目的に作られています。
なお、一口に「防音」と言っても、その機能は遮音と吸収、拡散に分けることができます。防音については、あくまでも概念的な言葉であり、その性能は遮音や吸音などの機能が組み合わさることで初めて発揮する物なのです。遮音については、文字通り「音を遮る」という機能で音を通さなくすることを指していて、吸音・拡散については、室内の音の響きをコントロールする機能を指していると考えてください。ちなみに、防音室を構成する建材について、遮音機能を担う建材の大半は、壁の中に施工されています。そして、事後的な防音対策として、防音室内の音響環境を整える目的で、吸音・拡散機能をもつ建材が使用されるのですが、これが防音壁材と言われます。
なお、防音室の壁について、遮音や吸音、どちらか一方の性能ばかりを重視した場合、以下のような問題が生じます。
- ・遮音を重視した場合
遮音は室外に音が漏れていくのを防ぐ機能です。そのため、防音室を作る際には、この部分の性能だけを高めれば良いと考える人もいます。しかし、遮音性能だけを重視した場合、音は室内にこもってしまうことになるため、音漏れは防げるものの、室内の音響環境が悪化してしまうことになります。 - ・吸音・拡散を重視した場合
吸音・拡散は、室内の音の響きをコントロールする機能を指しています。そして、この機能ばかりを重視した時には、防音室内での音の響きが失われてしまうため、自分の演奏音に違和感を感じるような音響環境となってしまいます。
防音室は、音漏れさせないことが大切であることは間違いないのですが、利用者が音を楽しめない環境になってしまうと、部屋の快適性が低下してしまいます。したがって、理想的な防音室を作りたいと考えた場合、遮音と吸音、拡散のバランスをきちんととらなければならないと考えてください。防音室内の音響調整は、高い技術と経験が求められるため、防音室工事が「専門性が高い」と言われているのです。
防音室に使用される防音壁材の種類について
それではここからは、防音室に使用される防音壁材の種類について解説します。防音壁材は、大きく分けると「仕上げ材として用いられる物」「下地材として使用されるもの」「後付けできる物」の3つに分けることができます。
防音室を作る際には、これらの防音壁材をうまく組み合わせることで、必要な防音性能や音響づくりの調整を行うのです。ここでは、主な防音壁材について、それぞれの特徴をご紹介します。
音響壁材(仕上げ材)
まずは、音響壁材と呼ばれるものです。防音壁材の中で最も認知されているものは、貫通孔加工がされた吸音壁材などでしょう。音楽教室などの仕上げ材としてよく利用されていて、穴から抜けた音のエネルギーを背後層の多孔質素材で吸収させることで吸音するという仕組みになっています。多くの場合、木材に多数の穴があけられている壁材が使用されているのですが、金属パネルに微細な孔がたくさんあけられている物もあります。
なお、快適な音響環境を作るためには、音を広げる機能に特化した拡散壁材も必要になります。防音室は、室内で発生した音エネルギーを吸収したり、拡散することで、利用者が快適な音に感じるように調整します。そして、仕上げ材として使用されるこれらの建材が、音響壁材と言われています。
なお、防音室の性能に関しては、音響壁材だけで調整するのではなく、下で紹介する下地材も組み合わせることでバランス調整が行われます。
音響壁材(下地)
防音壁材には吸音効果を持たせた音響壁材(下地)もあります。このタイプを使用する場合、表面的にはクロス仕上げとなります。ただ、この建材を使用する場合、音のエネルギーが通過しやすい織物クロスを使用することがポイントとなります。
吸音下地材は、多孔質素材となっていて、壁内に通り抜けてきた音エネルギーを、多孔質素材の部分で吸収するという仕組みになっています。
遮音壁材(下地)
防音壁材の中には、遮音専用の壁材もあります。遮音パネルや遮音シート、遮音マットと呼ばれる建材がこれに当たります。
なお、防音室を作り上げる際には、遮音機能ばかりを重視すると、室内に音がこもってしまうことになります。そのため、遮音下地材は、上で紹介した音響壁材や下で紹介する後付けの吸音パネルなどと組み合わせて使用するのが一般的です。
吸音パネル(後付け)
吸音パネルは、後付けできる吸音材で、防音壁が完成した後に、室内の音響調整を行う、動画配信者の方が簡易的な防音対策として使用する感じの建材になっています。
この材料は、基材に高密度の不織布やグラスウールなど、高い吸音効果を持つものが使用されています。防音室作りでは、家具などの配置が決まっていない場合もあり、そのような時には、防音室が完成してから、細かく音響を調整するため、改修工事として利用されるなどというケースが多いです。
最近では、デザイン性が良く、取り付けも簡易化された吸音パネルが販売されるようになっていて、オフィスの防音対策として会議室などに取り付けられるケースも増えています。
まとめ
今回は、防音室の防音壁の構造や、音響調整のためなどに用いられる防音壁材について解説しました。
防音壁と聞くと、とにかく音漏れしないように調整された壁のことをイメージする方が多いと思いますが、記事内でご紹介したように、単に音漏れしなければ良いというほど単純なものではないのです。防音壁が、全ての音を遮ることができるようになれば、確かに騒音トラブルの可能性が限りなく低くなるといえるでしょう。しかし、外に漏れていかなかった音は、室内で反響し続けることになるため、防音室の中にいる人が快適に過ごせなくなってしまうという別の問題が発生するのです。
楽器の演奏の上達を考えた時には、自分が出した音を聞くということも非常に重要とされています。したがって、防音室を作る際には、音漏れを防ぐことに合わせて、室内にいる人が自分の出した音にストレスを感じないよう、音響調整をすることも重要なのです。そして、この音響調整は、高い技術と経験がものを言うため、「防音室作りは非常に専門性が高い!」と言われ、専門業者に依頼すべきとされているのです。