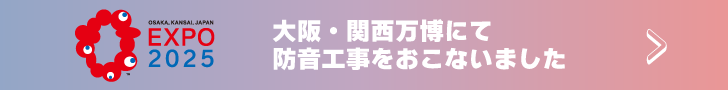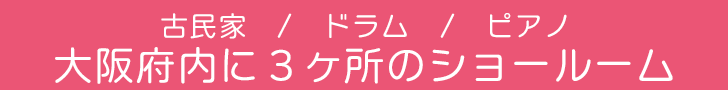吸音材は置くだけで効果がある?吸音材の種類と防音対策のポイント
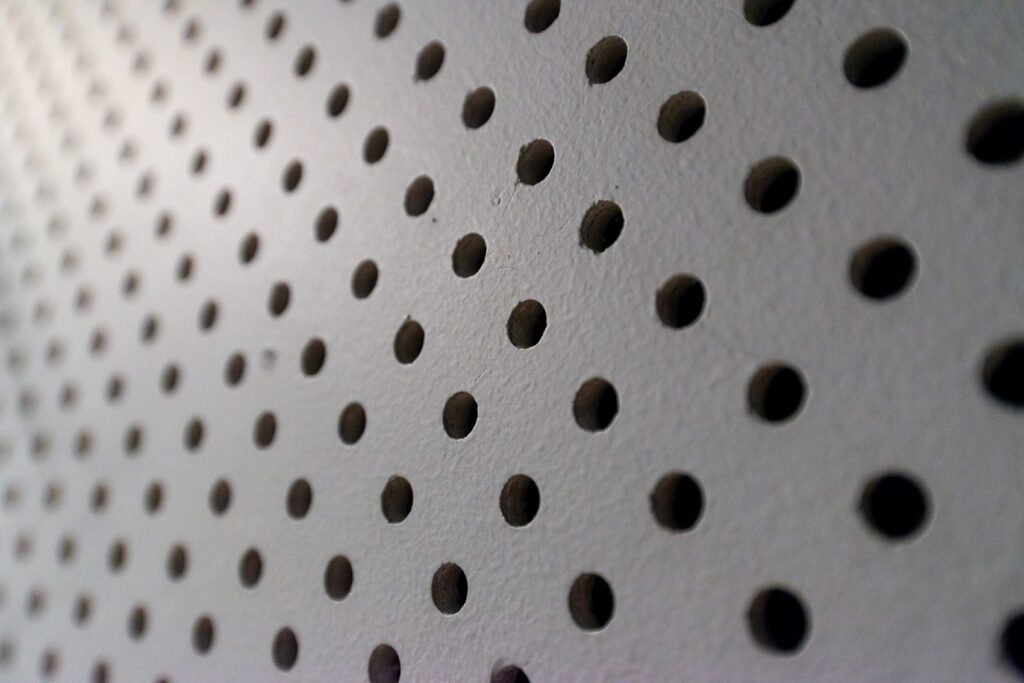
サンテレビ「アサスマ! 」で防音工事の匠が紹介されました!
安価に部屋の防音対策ができるアイテムとして人気なのが、ホームセンターなどでも簡単に手に入る吸音材と呼ばれる製品です。吸音材は、その名称から分かるように、音を吸収することで部屋の中の反響音を減らすというアイテムになるため、誰でも簡単に防音対策ができると注目されています。特に、賃貸住宅などに住んでいる方の場合、専門業者に依頼して本格的な防音工事を施すことができないため、市販されている吸音材などを利用して自分で防音対策を施そうと考える人が増えているのです。
ただ、安価で簡単に設置できるアイテムとは言え、吸音材をどのように設置すれば防音効果が得られるのかがいまいち分からない…という声を聞く機会が多いです。中には、「吸音材は置くだけで防音効果が得られる!」など、製品の機能を過大評価している方もいるようですが、当然、何も考えず部屋の中に吸音材を置くだけといった対策では思うような効果は得られないと考えておいた方が良いです。音も、大きく分けると空気伝搬音と固体伝搬音の二つに分けることができるのですが、どちらの音が問題になっているのかによって適切な対策が変わってしまうのです。
そこでこの記事では、安価で簡単な防音対策グッズとして人気になっている吸音材について、その種類やどのように使うべきかを解説します。
吸音材とは?その種類もご紹介
それではまず、吸音材がどのような製品なのかについて簡単に解説します。
冒頭でご紹介したように、吸音材は、その名称通り、音を吸収して音が響かないようにするためのアイテムです。吸音材を適切に設置することができれば、反響音や残響音を軽減するという効果を期待できるようになるのです。
ホームセンターやネット通販で販売されている吸音材は、多孔質(穴がたくさんある)の素材が採用されていて、音が吸音材に届いたとき、穴の中で音同士がぶつかり合うことで熱エネルギーに変換され、吸音材がそのエネルギーを吸収することによって音のエネルギーが少なくなる、つまり音が軽減されるという仕組みになっています。
なお、一般的に『吸音材』と呼ばれる製品にもいくつかの種類が存在するので、以下で代表的な吸音材とそれぞれの特徴をご紹介します。
多孔質系吸音材
住宅の防音工事で利用される吸音材として、最もポピュラーなのが多孔質系吸音材です。このタイプは、素材に細かな穴がたくさんあるタイプの素材で、その穴の中に音が入り込んだ時、穴の中で摩擦や振動が生じ、音のエネルギーが熱エネルギーに変換されることで音を吸収するという製品となります。なお、多孔質型の吸音材にもいくつかの種類があり、主に以下のような製品が利用されます。
- ・ロックウール
- ・グラスウール
- ・ウレタンスポンジ材
- ・フェルト
ロックウールやグラスウールは、断熱材として住宅の各所に使用される素材です。昨今では、高断熱の住宅が求められていることから、壁にはグラスウールなどが設置されています。そのため、外部からの音の侵入は、一昔前の住宅と比較するとかなり抑えられるようになっています。専門業者が行う本格的な防音室工事などでは、グラスウールが吸音材として主に使用されます。
振動板系吸音材
薄い板状の吸音材が、振動板系吸音材です。このアイテムは、音が吸音材に直接あたった時、吸音材内部で摩擦が生じ、それにより音エネルギーの一部が消費されて、吸音効果が得られるといった仕組みになっています。
ベニヤ板やカンバス(麻で織った荒い布)生地が代表的な振動板系吸音材とされているのですが、上述した多孔質系の吸音材などと比較すると、あまり高い効果は期待できません。振動板系吸音材は、あくまでも簡易的な対策として用いられることが多いです。ただ、下で紹介する共鳴型の吸音材とは相性が良く、これと組み合わせて使用するとそれなりの効果が期待できるとされています。
共鳴型系吸音材
共鳴型系吸音材は、空気そのものを振動させ、摩擦によって音エネルギーを消費させる「共鳴現象」を利用する吸音材です。このアイテムは、壁と吸音材の間に隙間を設けることで周波数の調整が可能になるため、幅広い音域の騒音、雑音を軽減することができます。一般住宅などで用いられる共鳴型系吸音材は以下のような製品があります。
- ・有孔ボード
- ・パンチングメタル
有孔ボードは、防音に興味のない方でも見たことがあると思います。これは、ボードの表面に無数の穴が設けられているもののことで、学校の音楽室や視聴覚室などの壁に良く使用されています。パンチングメタルは、ボードの素材がアルミや鉄、ステンレスなどの金属になっているもので、表面に無数の穴がある点は一緒です。
上記の通り、吸音材にもさまざまな種類の製品があります。より高度な吸音効果を期待する場合、どれか一つの吸音材を使用するのではなく、上手に組み合わせることで高い効果が期待出来ます。
吸音材で効果を期待できる音の種類
ここまでの解説で、吸音材がどういった製品で、どのような効果が期待できるのかが分かっていただけたと思います。吸音材は、音が素材の中に入るもしくは当たった際、音エネルギーを熱エネルギーに変換することで軽減するというものとなります。
ただ、注意しなければならないのは、吸音材で効果を期待できる音にも種類があるということです。先ほど紹介したように、音にも空気伝搬音と固体伝搬音という種類があるのですが、吸音材はこのどちらにも効果を期待できるアイテムというわけではないのです。空気伝搬音と固体伝搬音の特徴は以下の通りです。
- ・空気伝播音
人の声やTVの音声、自動車のクラクションなど、空気を振動させることで伝わる音が空気伝搬音 - ・固体伝播音
固体伝播音は、壁や床、天井など、衝撃を受けた物体の振動で伝わる音です。例えば、階下で聞こえる人の足音や物が床に落ちた時の音が固体伝搬音です。
固体伝搬音は、物体そのものが振動して音が伝わっていきます。つまり、吸音材を設置してもこのタイプの音を軽減することはできないのです。吸音材は、空気を振動させて伝わる空気伝搬音には効果的です。
吸音材は置くだけで効果が得られるのか?
それでは、部屋の防音対策を考えた時、吸音材を使用して音を軽減する方法についても簡単に解説します。吸音材は、音が当たった際、摩擦により音のエネルギーを熱エネルギーに変換することで軽減するアイテムと紹介しました。こう聞くと、「吸音材は、どこでもいいから置くだけで効果がありそう!」と感じてしまいますよね。
その結論は、吸音材は置くだけで一定の効果は期待できるとなります。ただ、吸音材の効果を最大限発揮させたいと考える場合は、適切な配置を考え取り付けることが重要です。部屋の中で何らかの音を出した際は、目には見えないものの壁や天井、床にぶつかって反響しています。そのため、その反響音を減らすことを考えると、音の反射が多い場所に吸音材を配置するのが良いのです。例えば、部屋の角の部分を中心に配置すると、多くの音が吸音材に当たるようになるため、反射音を効率的に吸収することができ、音の軽減効果が大きくなると考えられます。
なお、吸音材の設置に関しては、基本的に壁面に設置するようにしましょう。賃貸住宅などで使用される吸音材は、強力な両面テープを使って張り付ける感じになるのですが、この方法で天井に設置した場合、いずれ粘着力が低下して落下する危険が高いからです。
床面の対策については、固体伝搬音を防止できる防音マットと呼ばれる製品を利用するのがおすすめです。足音などを階下に伝わらないようにしたい…という場合、部屋の隅の床に吸音材を設置しても、それだけで固体伝搬音を防ぐことはできません。この場合、床材に伝わる衝撃をできるだけ少なくするため、床そのものに防音仕様の材料を設置するのが良いのです。カーペットなどでもある程度の効果が期待できるのですが、人の足音など重量衝撃音については厚手の物を設置しなければほとんど効果はありません。
まとめ
今回は、安価に部屋の防音対策ができる吸音材について、置くだけで防音効果が得られるものなのかについて解説しました。
記事内でご紹介したように、吸音材は、音エネルギーを熱エネルギーに変換することで音を軽減するアイテムです。そのため、部屋の各所に置いておくだけでも一定の効果を期待することは可能です。しかし、吸音材によって高い防音効果を期待するという場合は、きちんと配置を考えて設置しなければいけません。また、吸音材は、全ての音エネルギーを吸収できるアイテムではないという点も注意が必要です。吸音材のみの対策は、無い場合と比較すれば多少音が軽減されるものの、もともとの音の大きさが大きければ、吸収しきれない音は部屋の外に漏れて行ってしまいます。そのため、楽器の演奏やホームシアターなど、大きな音を楽しみたいと考えるなら、吸音材だけでなく、音を遮る遮音材も組み合わせて対策する必要があります。
賃貸住宅の場合、なかなか効果的な防音対策を期待することは難しいので、基本的には隣人に迷惑をかけるような大きな音を出さないようにするという、配慮が重要になると考えましょう。