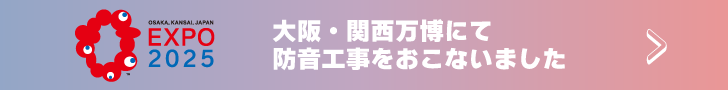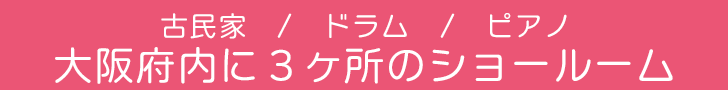防音室の寒さ対策について!快適な空間を作りたくてもストーブの使用は注意!

サンテレビ「アサスマ! 」で防音工事の匠が紹介されました!
今回は、快適な防音室を作るためにおさえておきたい寒さ対策について解説したいと思います。
一般的に、防音室はその他の居室と比較すると、気密性や断熱性が非常に高い空間となるため、防音室内の温度は室外の温度の影響を受けにくくなります。防音室は、高い防音性を確保するため、可能な限り隙間を無くす、壁の中にはしっかりと断熱材を充填するといった対策が施されるので、室外が寒い場合でも、防音室の中は暖かい環境が保たれやすくなるのです。
しかし、この状況はあくまでも防音室に関する一般的な傾向であり、絶対に寒くならないかというとそうではないのです。防音室の中には、換気用のファンの設置や室内の広さなどを理由に、室外の寒さの影響を受けてしまい、室温が下がってしまう環境になるケースもあります。そのため、快適な防音室を作りたいと考えた時には、必要に応じて寒さ対策を検討しなければいけないのです。
この記事では、防音室周りの寒さに関する情報と、暖房機器についてご紹介します。
防音室は楽器に合わせた温度・湿度環境を重視しなければならない
自宅に防音室を用意して楽器の練習をしたいと考えている方の場合、毎日長時間防音室にこもることになると思います。防音室は、その他の住宅リフォームと比較しても、かなりコストのかかる工事となるため、自宅に用意するとなると、きちんと利用しなければもったいないです。
それでは、防音室内に長時間滞在するという場合、どのような状況が望ましいのでしょうか?当然、寒すぎる環境の防音室になると、楽器の練習もままなりませんし、演奏技術の向上が見込めなくなってしまいます。そのため、防音室内の環境は、長時間の練習にも耐えられるような温度環境を維持できるようにすることも大切なのです。
ここではまず、防音室内の温度と湿度について考えてみたいと思います。
防音室の温度について
防音室内の温度管理については、エアコンを設置して、防音室を利用する際に最適と感じる温度に調整するという方がほとんどです。
しかし、エアコンの暖房機能を長時間稼動させ続けた場合、防音室内が極端に乾燥してしまうことになります。室内が乾燥しすぎると、楽器の部品の緩みや木材の反り・割れなどを引き起こすほか、場合によっては雑音・共鳴・調律変化などの問題が起こることがあるとされています。特に、アコースティックピアノは、木材が主に利用されている楽器なので、乾燥のし過ぎは注意が必要です。
人が滞在する場合は。25℃程度の室温を維持したいと考えるかもしれませんが、エアコンを使ってこの温度を維持し続けると乾燥しすぎる可能性があります。また、ピアノやドラムなどについては、最適な温度が10~20℃程度と言われているので、楽器の状態の維持を考えても、エアコンの設定温度は注意が必要です。可能であれば、ある程度の重ね着をしてでも、20℃前後に設定するのが良いかもしれません。
防音室の湿度について
防音室内の環境については、温度以外にも湿度に注意しなければいけません。あまりに乾燥しすぎるのも良くないのですが、湿度が高すぎる状態も良くありません。
防音室は気密性が非常に高い場所となるため、暖房を使う際は、加湿器を一緒に稼働させる方が多いです。しかし、加湿器を長時間使用すると、防音室内が高温多湿な状態になってしまい、楽器の木材部分の変形や金属部品のサビに繋がる可能性があるので注意しましょう。ちなみに、暖房機器としては石油ストーブやガスストーブなどもあるのですが、これらは水蒸気を発生させるため、防音室内での使用は望ましくありません。
ちなみに、ピアノやドラムについては、最適な湿度が35~65%とされています。
防音室内で使用する暖房器具について
住宅内で使用される暖房器具にはさまざまな種類が存在します。多くの方はエアコンを使って温度調整をすることを真っ先に思い浮かべますが、この他にも通常の居室では床暖房などが主流となってきています。
また、局所的な暖房で言えば、ストーブやヒーターなどが持ち運びもできて便利ですね。しかし、防音室内で使用する暖房器具として、石油ファンヒーターやガスストーブ、電気ストーブは注意が必要です。ここでは、防音室と暖房器具の関係性について簡単にご紹介します。
石油ストーブの注意点
寒冷地などでは非常に心強い暖房器具として現在でもよく利用されています。石油ストーブは、灯油を燃料として、燃料を燃やすことで熱を発生させる器具となります。
つまり、石油ストーブなど、灯油を燃焼させることで熱を起こすタイプの暖房器具は、熱と一緒に一酸化炭素を排出させるのです。防音室は、先ほど紹介したように非常に気密性の高い空間となるため、そこで石油ストーブを利用すると、室内に一酸化炭素が充満してしまい、そこにいる人が一酸化炭素中毒になる恐れがあるのです。一酸化炭素中毒を避けるためには、小まめな換気が必要となり、頻繁に練習を止め、窓やドアを開放しなくてはならなくなります。そのため、楽器の練習効率が著しく低下してしまう恐れがあるわけです。もちろん、一酸化炭素中毒を避けるため、ドアなどを開放した状態で演奏すれば、防音室が意味をなさなくなります。
防音室での石油ストーブの利用は、人の命を危険にさらすことも考えられるため、絶対に使用しないようにしましょう。
ガスストーブの注意点
次は、防音室内でのガスストーブの使用についてです。ガスストーブは、ガスを燃料とした暖房機器で、ガスを燃焼させることで熱を発生させます。
ここまで言えばわかると思いますが、ガスストーブも石油ストーブと同じく、稼働時に一酸化炭素を排出するのです。そのため、防音室内でこの暖房器具を使用すると、一酸化炭素中毒のリスクがあります。
石油ストーブと同じく、防音室内でのガスストーブの使用は厳禁です。
電気ストーブの注意点
最後は、電気ストーブです。局所的な暖房機として人気の電気ストーブは、放射熱で周囲を暖めるシステムになっています。そのため、石油ストーブなどとは異なり、一酸化炭素中毒の危険はありません。
ただ、電気ストーブは、空気よりも先に、壁や床、近くにある楽器などが先に温められます。そのため、室温が上昇するまでに楽器が熱くなってしまうことがあるので、基本的には推奨できないとされています。また、防音室内で、電子機器を多く利用する場合、タコ足配線となってしまい、それが元に火災が起きてしまうというリスクが生じるので注意しましょう。防音室は、コンセントの数が少なすぎた…という失敗をする方が意外に多いです。コンセントの数が少ないと、電気機材を利用する際に、タコ足配線にせざるを得なくなるので、防音室の計画をする際に、どれぐらいの電気機器を使用するのかよく考え、必要な数のコンセントを用意してもらうようにしましょう。
なお、電気ストーブはコンセントの切り忘れがよくある点も注意が必要です。ストーブが原因となる火災については、直接的に火が出る石油ストーブなどが多いと考えている方が多いはずです。しかし、東京消防庁の調査では、ストーブ火災の原因の7割以上が電気ストーブだったとされています。電気ストーブは、他のストーブよりも「安全」と考えてしまい、油断する方が多いようなので、スイッチの切り忘れや燃える物を近づけないなど、基本的な使い方に注意してください。
エアコンの注意点
防音室の暖房器具としてはエアコンが最もオススメです。防音室を作る際、一緒に設置してもらうほか、後付けでもエアコンを設置することが可能です。
しかし、防音室にエアコンを後付けする場合は、一般のエアコン設置業者に工事を依頼すると、防音室の性能が低下する恐れがあるので注意しましょう。エアコンを設置する場合、室内機と室外機を繋ぐため、壁に穴を空けます。当然、防音室の壁に穴が開くと、そこから音漏れするようになるので、防音性能は著しく低下してしまいます。パテなどで穴を埋めますが、隙間が完全になくなるわけではない為、一般の電気店のやり方では音漏れの多い防音室になってしまいます。
防音室の性能を維持したままエアコンを設置したいと考えるなら、、防音室の設計やリフォームに強い業者にエアコンの設置を依頼しましょう。この場合、ダクトを通す穴の開け方、ダクト周りの処理など、専門性の高い施工を行ってもらえるため、後付けでも防音室の性能低下を防ぐことができます。
まとめ
今回は、防音室の寒さ対策について、防音室に適した温度や湿度、また温度調整をするための暖房機器の注意点いついて解説しました。
防音室は、基本的には外気温の影響を受けにくい部屋となるので、冬場でも通常の居室よりは暖かい環境が維持しやすいです。しかし、真冬の氷点下になるような時期になると、暖房機器なしで防音室を利用することは難しくなるでしょう。したがって、防音室内を快適な環境に維持するためには、何らかの暖房機器の設置は必須と考えておきましょう。
なお、防音室の暖房に関しては、エアコンの設置が最もおすすめできるので、基本的には防音工事の際に一緒にエアコンを設置してもらうと良いです。防音工事の匠でも、エアコンの設置は基本工事の中に含んでいるため、安心して防音工事の相談をしてください。