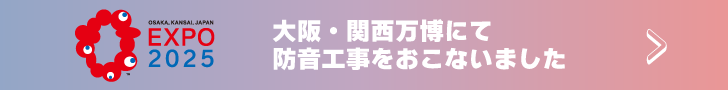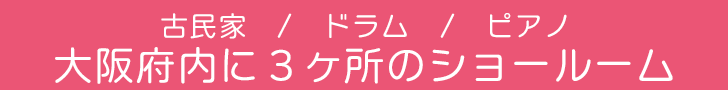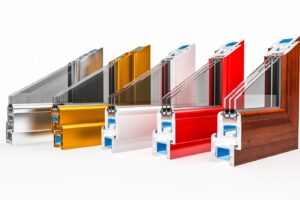ドアの防音対策!防音ドアの構造や選び方について

サンテレビ「アサスマ! 」で防音工事の匠が紹介されました!
防音室を作る際には、壁や窓に注目する方が多いのですが、同じ家に住む家族間の騒音トラブルを防止するためにはドア部分の防音にも注目しなければいけません。
壁や床、窓の防音対策をどれだけしっかりと行ったとしても、ドア部分の防音が不十分な場合、ドアから音が漏れてしまうことになり、防音室を作る意味がなくなってしまいます。実は、防音室の音漏れについては、ドアからの音漏れが約40%も発生しているという調査データがあるなど、防音室の利用用途に合わせて最適な防音ドアを選ばなければならないのです。ちなみに、防音仕様のドアでない場合、常に換気が行われるようにということが重視されるため、きちんとドアを閉めていたとしてもわざと隙間が生じるようになります。つまり、防音室には専用の防音ドアと呼ばれる製品を採用しなければならないのです。
ただ、防音ドアにもいくつかの種類が存在していて、採用する製品によってその性能が大きく変わります。そこでこの記事では、防音室の性能を左右する大きなポイントになるドアについて、防音ドアの構造や選び方を解説します。
防音ドアはどんな仕組みになっているのか?
それではまず、防音ドアと呼ばれる製品が通常のドアとどのような点が異なるのか、その構造について解説します。
重量が違う
防音ドアと通常の室内ドアを比較した際、最もわかりやすい違いが「重量」です。
防音ドアは、通常のドアとは全く異なる設計思想で作られているのですが、最大の特徴と言えるポイントが振動抑制構造にあるとされています。音は、空気の振動によって伝わっていくものなのですが、防音ドアは重量のある素材を利用することで、この振動を抑制するという設計が取り入れられているのです。
どれぐらい重量が違うのかというと、一般的な室内ドア(フラッシュドア)は平均的な重量が20kg前後と言われているのに対し、防音ドアは一般的なタイプで50kg以上ありますし、音楽スタジオなどに採用される本格的なものはドアだけで100kgを超えるような物もあるのです。防音ドアは、この重量によって音波がドアに当たったとしても振動しにくいため、音漏れを防げるようになるのです。
防音ドアは多層構造になっている
一般的な室内ドアは、2 枚の薄い合板または中密度繊維板 (MDF) で構成されるものが多く、内部に空洞があることで軽量さを実現している場合が多いです。しかし、防音ドアの場合、以下のように多層構造が採用されています。
- ・外装部分:頑丈な鉄板など
- ・中間層:吸音材、遮音シートが入っています
- ・ドア内部:空気層が用意され、追加の遮音効果や断熱効果が得られます
上記のように、防音ドアは、ドアの表面部分に遮音性の高い鉄板など、頑丈な素材が採用されていて、さらに内部は吸音材や遮音シート、さらに空気層を組み合わせることで、異なる周波数の音をブロックできるような構造となっているのです。
多重構造が採用されていることから、防音ドアは高音域から低音域まで、幅広い音域の音を防ぐことが出来るようになっています。
ドアを閉じた時の気密性の追求
先程紹介したように、一般的な室内ドアは、ドアを閉じていても換気が行われるよう、わざと隙間が生じるような作りになっています。皆さんの家にあるドアを閉めて確認してみればよくわかりますが、ドアの下部には1cmほどの隙間が生じているはずです。防音室の場合、この隙間は致命的な弱点になるため、ドアを閉じた時には、隙間をしっかりと埋められるような工夫が施されています。
例えば、防音ドアには特殊なゴムパッキンとマグネットシールが組み込まれていて、ドアを閉めた時にはパッキンがつぶれることで隙間を完全にふさぐ構造になっています。また、ドア下部に生じる隙間については、自動的に下降するドロップシールなどが採用されている製品があり、僅かな隙間さえも見逃さないようになっています。なお、防音ドアに使用されるシール材は、経年劣化しにくい素材が採用されているため、ドア部分の気密性を長期間保ってくれます。
ハンドルなどの付属品も特徴的
防音ドアは、開閉に用いるハンドルも防音性能に大きな影響を与えています。簡易の防音ドアの場合、通常のドアと同じようなレバーハンドルが採用されているのですが、この場合、気密性の面ではどうしても限界が生じてしまいます。
そのため、高性能な防音ドアなどの場合、ハンドルを回すことでドアを枠に引き寄せる機構を持つようなローラー締りハンドルが採用されます。音楽スタジオなど、最高峰の気密性が求められる場所では、複数点でドアを固定することが出来るグレモンハンドルが採用されています。防音ドアは、開閉に使用するハンドル部分など、付属品に関しても防音性に注目して、採用するタイプが選ばれているのです。
防音ドアの種類と選び方
防音ドアは、上で紹介したような対策が施されていることもあり、一般的な室内ドアと比較すると、高い防音性を確保できています。ただ、一口に防音ドアと言っても、いくつかの種類が用意されていて、用途によって採用すべき防音ドアの種類が変わります。
そこでここでは、主な防音ドアの種類と、実際に防音目的で導入する際の選び方について解説します。
防音ドアの種類
まずは防音ドアの種類についてです。防音ドアは、以下のような種類に分けることができます。
- ・簡易防音ドア
一つ目は、簡易防音ドアです。これは、生活音レベルの騒音問題を解消する目的で採用されるケースが多いです。減音効果は30dB程度なので、楽器用防音室のドアとしては少し性能が心もとないです。ただ、製品価格が10~20万円程度で、既存のドア枠を利用して取り付け可能など、導入しやすい防音ドアであるため、本格的な防音室までは不要という場合は、楽器練習用のドアとして採用されることもあります。 - ・音楽用防音ドア
これは、ドラムの演奏やプロ仕様のスタジオなど、本格的な演奏環境を整える必要がある防音室に採用される防音ドアです。減音効果が40~55dB程度あるので、マンションなどの集合住宅に防音室を作る場合にも採用できるレベルです。価格は安いものでも35万円程度で、高いものになると50万円以上するので、その点は注意が必要です。 - ・スライド式防音ドア
分かりやすく言うと、引き戸タイプの防音ドアです。このタイプは、省スペース設計である点や、バリアフリー対応が可能な点が大きな特徴です。ただ、構造が複雑になるため、価格が高くなる点が難点です。施工費まで含めると100万円以上かかることも珍しくありません。また、引き戸タイプの防音ドアは、レール部分の気密性の確保が難しく、また経年劣化が早くなるなど、特有の課題があるので、採用は慎重に検討しましょう。
なお、防音ドアは、素材による違いもあります。高性能な防音ドアの場合、スチール(鉄)が採用されるため、優れた耐久性とメンテナンス性が得られます。しかし、デザインの制約がある、価格が高くなるという点がデメリットになるでしょう。スチール製の防音ドアは、基本的には業務用の防音室に採用されるケースが多いです。見た目が無機質になりがちなので、一般住宅に採用すると見た目的に馴染みにくいという問題があるからです。
スチール製以外には、木製の防音ドアがあります。防音性能に関してはスチール製に劣りますが、一般住宅のインテリアともデザインが馴染みやすいですし、低価格で導入できるので取り入れやすいという点がメリットです。
防音ドアの選び方について
それでは、防音ドアの選び方についても解説します。なお、しっかりとした技術力持つ防音工事業者に相談すれば、お客様の利用用途に合わせて最適な防音室の性能を提案してもらうことができるため、基本的にお客様側で防音ドアを選ぶというようなことはありません。
しかし、提案された防音ドアが必要な性能を持っているのか確認するためには、なにを持って防音ドアを選べば良いのかは知っておく必要があるでしょう。
防音ドアを選ぶときには、防音室の利用目的を明確にする必要があります。なぜなら、防音室内で発生させる音の大きさが分からなければ、防音室に求められる性能値が分からないからです。例えば、楽器の演奏を目的とした防音室でも、ピアノの場合90~100dB程度の音量、ドラムになると110~120dBの音量になるなど、発生する音の大きさが大きく異なるのです。
したがって、防音ドアを選ぶときには、防音室内でどのような事をするのか、またそれによって発生する音がどれぐらいなのかを明確にしたうえで、その音が外に漏れないようにするにはどんな性能が必要なのかで判断するのです。以下に、防音ドアを選ぶときに確認しなければならないポイントをいくつかご紹介します。
- ・必要な遮音性能で選ぶ
防音室の性能などについては、Dr値(JIS規格)で表現されます。防音工事業者と打ち合わせしていれば「Dr-30」や「Dr-50」と言った言葉が出てくるのですが、これはDrの後ろにある数値の分だけ減音できるといった意味と考えてください。防音室内で発生させる音が、防音ドアの外でどれぐらいまで小さくなれば良いのかを考え、必要な性能を持つ製品を選ぶと良いです。 - ・防音室を使用する時間帯
防音室を使用する時間帯も防音ドアの性能選びをするときの検討要素になります。なぜなら、日中と夜間では音漏れが許容されるレベルが大きく変わるためです。日中は、人が活発に活動しているため、周りに多くの雑音が存在しています。そのため、防音室から多少の音漏れがあっても、周囲の雑音に紛れることで目立たなくなるのです。一方、人が寝静まる深夜帯になると、周囲が静かになる分、ちょっとした音漏れでも苦情が出てしまう可能性があります。したがって、日中しか使用しないという場合なら多少性能を落とした防音ドアでも構わない、夜間まで使用することを想定する場合、高性能なドアが必要となります。 - ・周辺環境によって選ぶ
防音ドアの性能は、周辺環境も関係します。例えば、戸建て住宅で隣家からはそれなりに距離が離れているという場合と集合住宅に作る防音室の場合では、求められる性能は大きく変わります。この他、自宅周辺に学校や塾など、静かな環境が求められるような施設がある場合も、高い防音性が求められます。
防音ドアは、基本的に屋内に設置する物なので、家族の理解度によっても求められる性能が変わります。例えば、家族全員が楽器の演奏を行うといったご家庭の場合、演奏音が自宅内に漏れている場合でも、それをうるさいとストレスに感じられる可能性は低いです。しかし、家族の中に受験生がいて、静かな環境が求められるという場合、しっかりと音を遮れるような性能が必要ですよね。
防音ドアは、防音室の中でどんな音を出すのか、またその音を出す時間帯がいつなのか、どの程度の音漏れまで共用してもらえる環境なのかに注目して選ぶと良いでしょう。
まとめ
今回は、防音室を作る際、重要なポイントになる防音ドアの基礎知識について解説しました。
防音ドアは、その構造や重量によって高い防音性能を発揮できるようになっています。記事内でご紹介した通り、一般的な室内ドアは、閉じていても換気が行われるということが重視されているため、音漏れを完全に防ぐことはできないのです。もちろん、ドアを閉めていれば、大部分の音を跳ね返すことができるので、生活音レベルの音なら小さくすることも可能です。しかし、防音室というのは、内部で非常に大きな音を出すことが想定されるため作られるわけで、多少の防音効果があったとしても、隙間から音漏れがするようでは意味のない物となってしまうのです。
防音ドアは、製品によって性能や価格が大きく異なるため、何の目的で防音対策を行うのかをよく考え、どのタイプを設置すれば良いのかを検討しましょう。