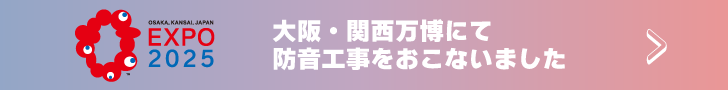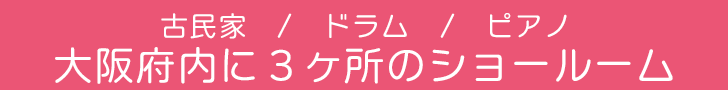防音床の構造について。集合住宅に作る防音室は床の防音が重要

サンテレビ「アサスマ! 」で防音工事の匠が紹介されました!
今回は、集合住宅に防音室を作る際、騒音トラブルを防止するためにも非常に重要な要素となる防音床の構造について解説していきます。
防音室を作る際には、壁の構造やドア、窓の構造に注目が集まりがちです。特に、ドアや窓は、音漏れの大きな要因となってしまうため、防音専用に開発された特殊な建材や構造が採用されることになります。例えば、窓に関しては、既存窓の内側にもう一枚窓を設置するという二重窓構造にされる、ドアに関しては閉じた時に可能な限り隙間を埋められる防音ドアに交換するといった対策が一般的です。
それでは、床部分の防音対策については、どのような手段が用いられているのでしょうか?特に、集合住宅における防音室の設置では、両隣だけでなく、上下も他の家庭と接することになるため、天井や床に関しても音漏れを防ぐためにしっかりとした防音対策を実施しなければならないのです。
そこでこの記事では、防音室で実施される床の防音対策について、防音床の構造について解説します。
防音室の床と一般的な床の構造の違い
それでは、防音室の床の構造がどのようになっているのかについて解説します。防音床は、一般的な居室の床とは異なる構造にすることで、高い防音性を確保します。
楽器の演奏を目的とした防音室について、特にピアノやドラムなど、楽器そのものが床面に接した状態で演奏するタイプは、音が振動となって床面に広がるという特徴を持っています。そして、床に広がった振動は、階下の天井に伝わってしまうことになり、上下階の住人同士で騒音トラブルが発生するわけです。実際に、集合住宅でピアノを演奏する際には、両隣から苦情がない場合でも、階下の住人から騒音に関する苦情が出るケースの方が多いとも言われています。
そのため、楽器そのものが床面に接した状態で演奏する場合、壁や天井だけでなく、床面の防音・防振対策をしっかりと行う必要があると考えてください。そこでここでは、一般的な居室の床の構造と、防音室の床の構造の違いについて解説します。
居室の床の構造について
まずは、一般的な居室の床の造りです。一般的な床の場合、そこまで複雑な構造をしているわけではなく、複数の材料を重ねるようにして作られています。
一般住宅の床の場合、最も下の部分にコンクリートがあります。いわゆる基礎と呼ばれる部分となるのですが、このコンクリート基礎の上に、根太(ねだ)や大引きという下地材が並べられて行きます。そして、大引きと大引きの間に、断熱材を設置することで、部屋の断熱性を高めます。ちなみに、床部分の断熱材は発泡プラスチック系の材料が採用されることが多いです。
この上に、構造用合板(捨て張り合板、下地合板)とフローリング材を敷けば、一般的な居室の床が完成します。ちなみに、最近人気の床暖房機能を搭載する場合は、構造用合板とフローリング材の間に床暖房システムを設置します。
楽器の演奏など、大きな音を生じさせるわけではない場合、上記のような構造の床を作っておけば特に問題はおきません。マンションなどの集合住宅で、室内を子供が走り回るなんてことになれば、振動音が階下に伝わり苦情が出る場合もありますが、通常の生活音レベルなら騒音トラブルにまで発展する可能性は低いです。しかし、楽器の演奏などを想定した防音室の場合、この構造では階下に音や振動が伝わってしまう可能性があります。
防音室の床の構造
次は防音室の床の構造についてです。一言で言ってしまうと、防音室の床は、通常の居室と異なり、二重床構造となっています。本格的な防音室は「部屋の中にもう一つ部屋を作る」と表現されているように、壁や天井はもちろん、床も二重構造になっています。
一般的な居室の床は、複数の材料を重ねて作られていますが、これらの材料はセットとして使われるのが一般的で、床としては一重構造と解釈されます。これに対し、防音室の床については、既存の床の上にもう一つの床を作るといった感じとなり、いわば二重の構造になっているのです。また、一般的な居室の床には採用されることのない材料も使って二重床を作ります。ちなみに、防音室を作る際に採用される二重構造の床については、二重床などと呼ばれています。
二重床の構造については、複数のやり方があるのですが、一般的な手法としては、防振ゴムや石膏ボード、吸音材に遮音シートなどを組み合わせた構造が採用されることが多いです。もともとある床を解体し、構造用合板とフローリングの間に、防振ゴム、吸音材⇒石膏ボード⇒遮音シート⇒石膏ボードと言った感じに、材料を重ねて施工していき、二重構造が実現します。防振ゴムの部分で、縁切りされることで、階下に振動が伝わらなくなります。
このように、防音室の床は、一般的な居室の床とはかなり構造が異なります。床面に接した状態で演奏を行う、ピアノやドラム用の防音室の場合、この二重構造の床が採用されると考えておきましょう。
防音床を構成する建材について
上述しているように、防音室の床は、一般的な居室の床には使用されない材料が多く採用されています。ここでは、防音室用の二重床を作るために使用される材料についても簡単にご紹介します。
- ・吸音材
吸音材は、いわゆる断熱材のことです。一般的な居室の場合、発泡スチロール系の断熱材が採用されているのですが、防音室の場合、幅広い周波数の音域において優れた吸音性能を発揮するグラスウール系の断熱材が吸音材として使用されます。 - ・防振ゴム
防振ゴムは、振動の伝わりを遮断する目的で使用されるゴムです。楽器から床に伝わった振動を、ゴムが吸収することで階下に振動が広がるのを防ぎます。 - ・石膏ボード
石膏ボードは、住宅のさまざまな場所に採用される材料なので、防音室特有の建材というわけではありません。石膏を主成分とした建材で、遮音効果や断熱効果が高く、なおかつ材料価格が安いことから、さまざまな場所で採用されています。石膏ボードの遮音効果については、材料が厚くなるほど高くなります。なお、防音室の床には、通常2枚の石膏ボードが採用されることになり、間に遮音シートが挟まれます。 - ・遮音シート
遮音シートは、その名前から分かるように、遮音を目的としたシート状の建材です。防音床の場合、上で紹介した2枚の石膏ボードの間に挟まれるように設置されます。それにより、床の遮音効果がさらに高くなるという効果が期待できるのです。この遮音シートについては、床だけでなく、壁や天井などにも採用され、高い遮音効果がある防音室になります。なお、遮音シートの性能については、素材の厚みよりも密度によって左右されます。
防音床は、上記のような建材が組み合わさることで高い効果を発揮します。
まとめ
今回は、防音室を構成する防音床の構造について解説しました。記事内でご紹介した通り、防音室の床は、一般的な居室の床とはかなり異なる構造となっています。
居室の床と防音室の床の違いは、一重構造か二重構造になっているかが最大の違いと言って良いでしょう。防音室用の床は、床が二重に作られることで、物理的に音を防ぐ能力が高くなるうえ、防振ゴムなどにより縁切りされることで振動が伝わりにくくなっているのです。先程紹介したように、ピアノなど、床面に接している楽器については、両隣の住居から音に関する苦情が出るよりも、階下から振動音に対する苦情が出るケースの方が多いとされているのです。
そのため、集合住宅に楽器用の防音室を作る場合には、きちんと振動音をシャットアウトできるような構造が求められると考えてください。