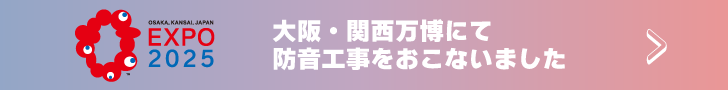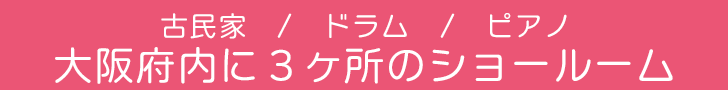防音室の湿気対策についてご紹介します!

サンテレビ「アサスマ! 」で防音工事の匠が紹介されました!
今回は、防音室の湿気対策に注目して、これから防音室を自宅に作りたいと考えている方が押さえておきたいポイントについて解説します。
防音室は、室内で発生する大きな音を外に漏らさないようにするということが最も重要な要素となるため、通常の居室とは異なる考えのもと設計されています。一般的な居室は、出来るだけそこに滞在する人が快適に、また健康的に過ごせるということが重視されるため、適度に室内の空気が入れ替わるように換気効率のことなどが考慮されます。しかし、換気が行われるということは、室内外において空気の行き来があるということを意味しているため、音も室外に漏れて行ってしまっているのです。防音室は、この空気の行き来を可能な限り少なくするため、非常に高い気密性が確保されています。そのため、室内で発生した音は、室外に漏れていかなくなるという構造になっているわけですね。
ただ、防音室のこの気密性の高さは、室内に湿気がこもりやすくなってしまうという問題を生じさせます。通常の居室のように換気がなされることがなく、空気のやりとりが少なくなれば、湿気の逃げ道もなくなってしまい、徐々に防音室内の湿度が高くなってしまうのです。
そこでこの記事では、防音室に湿気がこもることで生じる問題や、湿気を溜めないようにするためにはどうすれば良いのかについて解説したいと思います。
防音室は湿気対策が必要?
まずは、防音室に湿気対策が必要なのかについて解説します。結論から言ってしまいますが、防音室は湿気対策が欠かせないと考えておきましょう。
防音室は通常の居室とは違う!
冒頭でご紹介したように、防音室は「音漏れを防ぐ」ということを最大の目標として作られています。一般的な居室と比較すると、音が外に漏れていかないようにするため、可能な限り隙間を少なくして非常に高い気密性が実現されているのです。音は、空気を振動させて伝わっていくため、防音室では、この空気の出入りを可能な限り少なくするという特殊な構造になっています。
ただ、「音が漏れない=空気が漏れない」という構造は、防音室の中からあらゆるものが漏れ出ないようになるということを意味しています。例えば、防音室の中に人が滞在していて、呼吸や汗をかくことで湿気が増えてしまっても、高い気密性を誇る防音室では、音と一緒に湿気もこもってしまうことになるのです。
皆さんもご存知の通り、湿気が多い部屋になると、カビの発生、繁殖などの問題が生じてしまいます。防音室内でカビが繁殖すると、空気中にカビの胞子がたくさん飛び交うことになり、そこで活動する人間が吸い込んで、アレルギー症状を引き起こすなどの健康被害が生じる可能性があります。また、防音室の湿気が高まると、壁内結露が発生することで、防音壁の中に施工されているグラスウールなどの吸音材にもカビが発生することが考えられます。この場合、本来吸音材が持つ効果がどんどん低下してしまうことになり、防音室の性能そのものが低下することになるのです。
さらに、防音室内に湿気がこもってしまうという状況が、楽器にも悪影響を与えます。楽器の演奏用に作る防音室の場合、ピアノやドラム、ギターなどを防音室内で保管するというケースが多いのですが、湿気によりこれらの楽器が劣化してしまう可能性があるのです。
これらの問題のことを考えると、防音室は徹底した湿気対策が必要になると言えるでしょう。
防音室の湿気は楽器にも影響を与える!
楽器の演奏を生業にしているなど、楽器に関する知識を持っている方であれば、楽器は「乾燥が大敵」であるということをご存じのはずです。ただ、楽器の弱点が乾燥であるとはいえ、必ずしも湿気の高い場所で保管すべきであるという意味ではないのです。上でもご紹介しているように、湿気がこもり高湿状態の場所で楽器を保管した場合も、本体や音の劣化を招く恐れがあるのです。
例えば、多くの部分に木材が採用されているアコースティックピアノの場合、響板が湿気を吸うと、響板自体が膨張することで特に中音域の弦が引っ張られてしまうことがあるとされます。また、湿気により金属部分にサビが生じたり、弦が切れてしまうといった問題が生じることもあるそうです。この他、全体が木材で作られているアコースティックギターなどは、ネックが反ったり、リフレットが浮く、金属部分がサビてしまうなどの問題が生じる可能性があります。
楽器を保管する場合、乾燥を防ぐだけでなく、理想的な湿度環境を維持するということが重要です。人が快適に過ごせる湿度状況は、40~60%前後とされていますが、楽器についても50%前後の湿度が最適とされているため、湿気がこもりすぎるというのは何らかの対策が絶対に必要と言えるわけです。
ちなみに、高温多湿な気候とされる日本は、年間の平均湿度が60~70%程度とされています。この数値は、先ほど紹介した楽器や人が好ましいと感じる湿度よりも高いですよね。つまり、楽器保全のことを考えると、乾燥対策を検討するのではなく、むしろ湿気対策を検討することが大切な訳です。
防音室は湿気対策について
それでは、防音室に湿気がこもらないようにするためにはどのような対策を検討すれば良いのかも考えていきましょう。ここでは、防音室の湿気対策として有効な方法をいくつかご紹介します。
小まめな換気
防音室の湿気対策として、もっとも単純で簡単な方法が小まめな換気です。通常の居室の湿気対策でも、適度に換気を行うという方法が推奨されているように、防音室の湿気対策でもこの方法が最も有効と言えます。
先程から紹介しているように、防音室は音を漏らさないようにしなければならないという、部屋の目的からどうしても湿気がこもりやすくなります。自然に換気が行われ湿気がこもらないような環境にしてしまうと、音も一緒に漏れて行ってしまう訳なので、防音室の意味がなくなってしまいます。
したがって、防音室内の環境を良好に維持するためには、人為的に小まめな換気を心がけることが大切です。例えば、長時間防音室内に滞在するという場合でも、1時間おきに休憩を入れて扉を開放するなどという方法が有効です。また、防音室を使い終わった時には、扉を開けておくだけでなく、室内から室外に向けてサーキュレーターを回し、強制的に湿気を排出するなどという方法も有効です。防音室内に人が滞在すれば、呼吸や汗によってどうしても湿気が高くなっていきますので、それを効率的に排出すると良いです。
なお、防音室の性能のことを考えると、換気扇を設置して換気を行うのは難しいと考えている方が多いです。しかし、換気扇の中には防音仕様のものがあるので、そのタイプを設置してもらうのも一つの手です。
防音室の設置位置を工夫する
実は、防音室の湿気対策を考えた時には、どこに防音室を設置するのかで湿気のこもりやすさが変わります。つまり、防音室の設置場所を工夫することが、自然と湿気対策になるのです。
例えば、窓が近い場所や西日が当たる場所は湿気が発生しやすいです。また、自然光が当たらない北側の部屋は、その周辺が高湿状態になりやすいという問題があるので、なるべく避けた方が良いです。
防音室は、屋外に音漏れさせないことを考えると、家の奥の方が設置場所に適していると考えられがちですが、風通しが悪い場所は、湿気がこもるので望ましくありません。したがって、防音室の設置場所を検討する時には、出来るだけ通気性の良い場所を選ぶようにすると、湿気に悩まされにくくなります。ちなみに、これはユニット型防音室を設置する場合の話です。
除湿機を回す
居室の湿気対策では、除湿機を設置するという方法も非常に有効です。一般の居室でも、梅雨時期など、湿度が高くなる季節になると、除湿機を稼働させているお宅が多いはずです。機械が自動的に空気中の湿気を除去してくれ、快適な環境作りを助けてくれます。
そして、防音室に関しては、先ほど紹介したように、常に湿気がこもりやすいという環境になるため、利用時は季節に関係なく除湿機を利用することが推奨できます。最近の除湿機は、簡単に持ち運びできるような大きさの製品でも、除湿機能が高いものもありますし、空気清浄機能や加湿機能まで備えたものがあるので、1台用意しておくと防音室以外でも活躍してくれるはずです。
まとめ
今回は、防音室の湿気対策について解説しました。防音室は、室内で発生した音が外に漏れていかないようにするため、高い気密性が確保されています。ただ、気密性が高いということは、空気の出入りが少なくなるということを意味するため、防音室内で湿気が発生した時には、どうてもこもってしまいやすくなるのです。
湿気がこもり、室内の湿度が高くなると、そこに滞在する人が不快に感じるようになるだけでなく、カビの繁殖や楽器の劣化に繋がるなど、大きな問題が生じします。したがって、防音室は湿気がこもりやすいということを意識しながら、利用する際は湿気対策を実行しましょう。